1.はじめに 今年(2011年)、NHKの大河ドラマで「江−姫たちの戦国」が放映 されています。漫画チックな内容ですが、歴史を振り返ってみるきっかけと して楽しめばいいのでしょう。 そこで、お市さんや江姫などの縁の地である湖北を、俳句仲間と訪ねてみ ました。 2.時代背景 今回は姉川の古戦場跡と小谷城址を訪ねますので、時代背景をざっと眺め てみます。 1568年(永禄11年)− お市が長政に嫁ぐ 1570年(元亀元年) − 姉川の戦い(あねがわのたたかい) 1573年(元亀4年) − 江姫の誕生 1573年(元亀4年) − 小谷城の戦い、浅井長政没 1582年(天正10年)− 本能寺の変、織田信長没 1583年(天正11年)− 賤ヶ岳の戦い、柴田勝家とお市没 (1573年は元亀4年から天正元年に改元されています) 兵たちが駆け巡った戦いの場は湖北、つまり琵琶湖の北部一帯です。 浅井長政が小谷山に構えた城を取り巻くように湖北の平野が広がっています。3.姉川古戦場跡 北陸自動車道の長浜ICを出て国道365号を北西に少し進むと、姉川の 古戦場跡に着きました。 元亀元年(1570年)の夏、浅井・朝倉軍と織田・徳川軍が姉川を挟ん で対峙し、激しい戦闘を繰り広げた場所です。
←姉川古戦場跡の表示 ↓姉川 後方奥に伊吹山 (撮影:2010年4月末)
この日は雲一つない晴天でした。 姉川堤防の桜並木は満開で迎えてくれました。 北西方向に眼を移すと、小谷城址のある小谷山が見えました。 手前右の大依山(おおよりやま)は、姉川の合戦のとき、長政が陣を構えた 山だそうです。
←姉川堤防の桜並木 ↓小谷山(左奥)と大依山(手前右)
4.浅井歴史民俗資料館 NHKの大河ドラマに因み、長浜市は「江・浅井三姉妹博覧会」と銘打っ て3か所に特別展示場を設けています。浅井歴史民俗資料館(浅井会場)で の「江のドラマ館」、小谷山麓(小谷会場)の「江のふるさと館」、そして 長浜市街(長浜黒壁会場)の「歴史ドラマ50作館」です。 今回は時間の関係から浅井会場と小谷会場だけを訪問することにしました。 この日は子供歌舞伎で有名な曳山祭りに当たっていたため、車で長浜市街に 入るのを避ける意味もありました。 浅井歴史民俗資料館は古戦場跡から国道365号を北西に3キロほど走っ た所にありました。姉川に合流する草野川沿いにあります。資料館は大依山 (おおよりやま)に半円状に囲まれている感じです。
←大依山を背にした資料館 ↓
庭を囲むように郷土学習館、七りん館、糸姫の館が建っていました。 大河ドラマの影響で、次々にお客様が訪ねてきました。ここには知り合いの 女性Nさんが勤務しています。お市の方を凌ぐ美人のNさんは、多忙にもか かわらず、館内を親切に案内してくれました。言葉のはしばしから、Nさん が郷土を大切にしている想いが感じられました。 本館の郷土学習館では浅井氏三代の盛衰記、姉川の合戦、浅井三姉妹など を紹介、七りん館は築200年余りの民家を移築したもの、糸姫の館では養 蚕の歴史や仕事振りを紹介しています。
←資料館本館 ↓移築した古民家(七りん館)
かつて浅井地区は養蚕が盛んだったそうです。 群馬県の養蚕農家で育った私は、養蚕の様子を見学するのは感慨深いもので した。この地区では現在も1軒だけ養蚕を続けているそうです。賤ヶ岳の麓 の木之本では、絹糸を使った邦楽器の弦を製作しています。
←糸姫の館 ↓屋内展示(パンフレットから)
先日、日本における養蚕の現状を少し調べたことがあります。 農林水産省の統計データによれば、平成20年(2008年)の収繭量は約 380トン(昭和初期最盛時の千分の一)、養蚕農家数は約1000戸(最 も多いのは群馬で400戸余り)とのことでした。 5.小谷城址 浅井歴史民俗資料館から国道365号を北西へ約5キロ走り、小谷山の麓 に着きました。長政の祖父・浅井亮政(すけまさ)は小谷山の頂上に大嶽城 (おおづくじょう)を築きましたが、浅井長政が構えた城は小谷山の中腹に ありました。
A:番所址 標高約300m (シャトルバス終点) B:本丸址 標高約350m C:頂上 標高495m 小谷山の中腹まで車道がありますが、博覧会の会期中(1月15日〜12 月4日)は自家用車は通行できません。山の麓から番所址まで小型のシャト ルバスが運行されています。バスには、浅井家の家紋入りユニフォームを羽 織ったボランティアガイドさんが同乗しました。
←満開の桜 ↓ガイドさんの乗ったバス
番所址から本丸まではガイドさんの案内に従って歩きました。 麓を見下ろすと、歴史に登場した場所が真近に見えました。彼方に琵琶湖が 広がっていますが、逆光のためほとんど写っていません。 ↓正面に虎御前山 ↓右手奥に山本山、湖に竹生島
虎御前山と山本山を一緒に見ていただきましょう。 虎御前山(標高224m)に陣を構えた織田軍は、山本山城が秀吉の調略に 落ちるや、小谷城を攻め落としたのだそうです。姉川の戦いから3年後のこ とです。 A:虎御前山 B:山本山 C:清水谷 D:琵琶湖 E:竹生島 F:北国往還道 G:北陸自動車道 H:戦国歴史資料館
小谷山のふたつの峰の間に清水谷Cがあり、右手前まで入り込んでいます。 浅井家と家臣は、平時はこの清水谷で暮らしていたようです。茶々と初はこ こで誕生したものと思われます。
←ドラマで長政と江が散歩した辺り ↓小谷山頂上
発掘調査の結果、小谷城は火災には遭っていなかったようです。 NHKのドラマは、一般の人が抱いているであろうイメージに合わせて城を 炎上させたのだそうです。 また、江姫は城内で生まれたことが、発掘調査の結果からも推測されてい るそうです。
←大広間址 ↓本丸址
6.おわりに 小谷城は(炎上せずに)落城した後、秀吉が拝領しました。 しかし、秀吉は長浜城を築いて小谷城を廃城にしました。湖上交通の便を重 視したため、琵琶湖から離れている小谷城を嫌ったのでしょう。築城にあた っては小谷城の資材を利用したようです。 湖北にはゆったりとした風景が広がっています。 歴史上の人間模様などに思いを馳せると、一層風景に愛着が感じられます。 小谷山の麓の桜の花の下で、「湖北」という笛の曲を吹いてみました。 (散策:2011年4月13日 脱稿:2011年4月30日) ご参考:既報の湖北関連記事 ・長浜城 −−−− 長浜城 ・田川カルバート −− 田川、姉川、高時川など ・湖北の冬景色 −−− 冬の湖北の風景 ・雨の森芳洲庵 −− 朝鮮通信使と雨の森芳洲庵 ------------------------------------------------------------------ この稿のトップへ 報告書メニューへ トップページへ
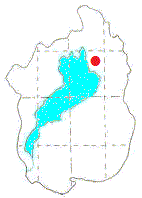
.jpg)